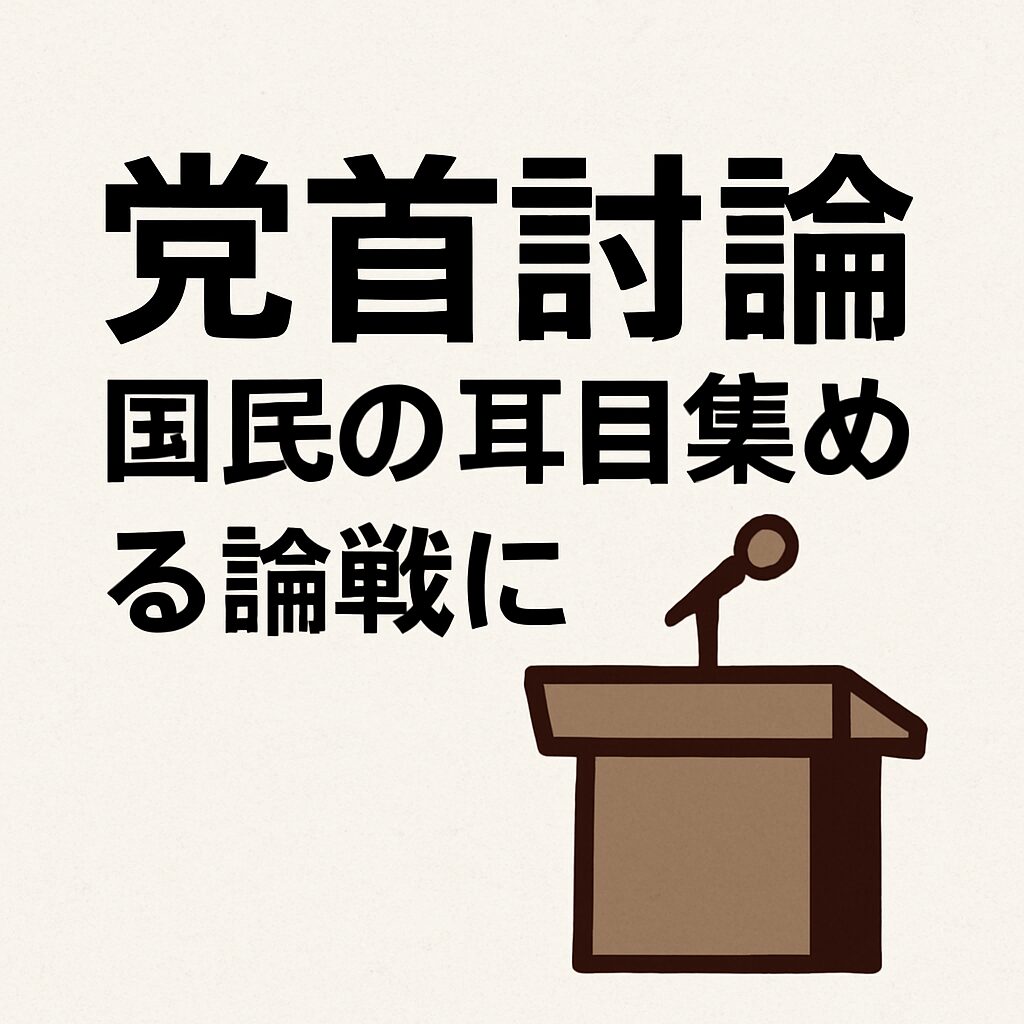
4月23日、久しぶりに開かれた国会の党首討論。
石破茂首相と野党3党の代表が向き合い、至近距離での論戦が行われました。
しかしその一方で、討論の制度面での課題も改めて浮き彫りに。
たとえば、持ち時間。
立憲民主党が30分に対し、国民民主党はわずか6分──。
たった6分で、国民の生活の“今の悩み”をどう伝えるか。
そんな限られた時間の中で、玉木雄一郎代表の言葉には確かな光がありました。
「取って配って、また取るんですか?」
「ガソリンの暫定税率はいつ廃止するのか」
「(税を)取って(補助金を)配ると無駄が生じるから、減税をやろう」
「北海道の人と話したが、“10円引き”ではがっかりしていた」
玉木代表は、政府が5月から実施予定のガソリン補助金10円引き下げについて、
“その場しのぎ”でしかないことを指摘。
「取って配る」という矛盾した政治の構造を、
誰でもわかる言葉で、たった一言で突きました。
「選挙に不利だから年金改革をやめるのか?」
もう一つ大きなテーマが、就職氷河期世代への年金改革。
「正社員になれなかった氷河期世代は厚生年金の保険料を十分に払えていない。
最低限の年金を保障する意義があったのに、選挙が近づいて不利だからやめるのか」
この言葉は、怒りというより“深いため息”に近いものでした。
過去の政策の失敗で不安を抱える世代を、
またもや選挙の都合で切り捨てようとする姿勢。
そこに玉木代表は明確に「NO」を突きつけました。
拍手じゃなくて、行動で示してくれ
討論の中で、自民党席から拍手が起きた場面も。
「自民は拍手してる場合じゃない」
この一言も、ズバリでした。
拍手ではなく、「どう変えるのか」を語るべき──。
玉木代表の言葉には、そうした“国民の視点”が貫かれていました。
討論制度にも課題──質と時間を見直すべき時では?
今回の党首討論、テーマは濃くても、制度面ではまだまだ改善が必要だと感じました。
- 持ち時間の格差が大きすぎる
- 野党の持論発表だけで終わってしまうケースも
- 首相の答弁が曖昧すぎる場面もあった
せっかく定期開催が始まったのに、
このままでは「予算委員会と変わらない」との批判も出かねません。
“夜間開催”や“反問形式の導入”など、制度そのものの見直しも進めてほしいところです。
最後に──限られた6分でも、国民の声は届く
6分。
この短い時間でも、生活の不安やモヤモヤは、
“本気の言葉”でなら伝えられる。
そう思わせてくれたのが、今回の玉木代表の討論でした。
討論の模様は、YouTubeで視聴できます。
実際のやりとりを、字幕付きでご覧になってみてください。
また、国民民主党の他の見どころ動画もおすすめです。

